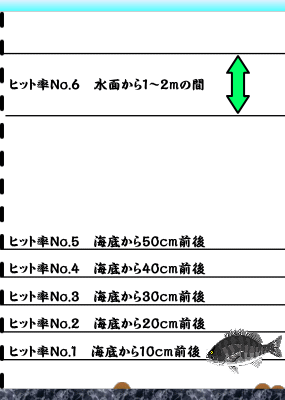師匠から教わった落し込み釣りは、この題名の通り『秘伝』です。
このサイトを立ち上げるまでは・・・ですけど・・・。(‾o‾)
黒鯛の落し込み釣りをはじめて教わった際、「この釣り方は決して他人に教えるな!」と、師匠の教えがありました。
しかし現在は、加入している釣りの会(東京湾黒鯛研究会)の会則にある、
「落し込み釣り発祥の地である、関東流.落し込み釣りの業を後世に受け継いで行く」との基本方針を実行する為、、講習会などで皆さんに説明する機会が増えてきました。
ここで記載するHPの文章では、落し込み釣りの核心部分と神髄(奥義)を5割程度しかお伝えすることができません。
残りの5割を取得するには、実際の釣り方を目で見て覚えるしか方法がないことが、この釣りの難しさだと思います。
■師匠の教え方
初めてこの釣り方を教わった時に感じた事は、まるで中国の拳法を師匠から伝授されるようでした。
まるでジャッキーチェンの映画のように・・・。
| ■秘伝の奥義 (アニメ北斗の拳なら、一子相伝の奥義って感じ(‾o‾) |
| □落し込みが上手くなりたければ、他の釣り人の釣り方は絶対に真似してはいけない |
| □私(師匠)の釣り方を目に焼き付け、教えた通りの釣り方をすれば必ず釣れるようになる |
| □一度覚えたこの釣り方は、決して他人に教えてはいけない |
この説明を聞いた時は、すごく緊張しました。(‾o‾)
私が、「なぜ他人の釣りを真似してはいけないのか?」と尋ねると、
「落し込み釣りで最も重要なのは、基本動作と基本行動」
「他人の釣り方を真似すると変なクセが付き、釣れない釣り方を実践する恐れがあるからだ!」
と、ゆうようなことを言われました。
また、「なぜ他人に教えてはいけないのか?」と理由をたずねると、
「皆が釣れるようになると、自分の竿に掛かる魚の数が減ってしまうからだ!」との事でした。
「ウ〜ワ〜、セコイ考え方!」と脳裏でつぶやき、
この回答を聞いた時には、安心感から大笑いしてしまいました。 アハハ・・・
■秘伝の釣り方
神奈川県.野島堤防での釣り方です。 水深は3〜4mと考えて下さい。
| ★奥義 その1 基本動作と基本行動 |
| ①エサを水面から自然なスピードで底まで落とす。 |
| ②エサが海底(ベタ底)に付いたら仕掛けをスーっと優しく上げる。 |
| ③2〜3m外れた場所に仕掛けを再投入する。 ⇒この行動を繰り返す。 |
| ④魚が掛かったら、竿を上げた時に手応えがあるからスグ分かる。 |
| ⑤アタリの殆どは止まるアタリなのでラインが沈まなくなる。 イメージとしては、エサが底に着底した時と同じような状態となる。 、まあ、何匹か魚を釣れば分かる。 |
なんとビックリ! 釣り方の基本は、これだけでした!
「これのどこが秘伝なの?」って感じです。
私が、「たったコレだけなの?」と聞くと、
「そう、これだけ。 もちろん、これ以外に狙い場所の選択がある」とゆうよ様なことを話していました。
しかし、なぜこれだけで良いのか?
その理由がわかった瞬間、「ナルホドね!」と納得できました。
| ★詳しく説明すると | |||||||||||||
| ①の「エサを水面から自然なスピードで底まで落とす」が最も重要でした。 このエサを、いかに自然なスピードでに落とすかで、釣れる/釣れないが決まります。 このスピードは、早くても遅くてもダメなのです。 そう、このスピードが”秘伝”だったのです。 師匠の釣り方は、どんな状況でも海面から底まで常に一定のスピードでエサを落として行きます。 この事により、全ての水深を釣れる可能性の高いスピードで探る事ができます。 なので、他の釣り人の釣り方を参考にしてしまうと、黒鯛が警戒する『釣れないスピード』を覚える可能性があるので、「他人の釣り方は真似するな!」だったのです。 もちろん、活性の高い黒鯛に対しては、エサの沈降スピードが速かろうが遅かろうが捕食してくれます。 しかし、極普通の条件では、違和感のあるエサに警戒し捕食行動を取りません。 そう、違和感を感じたエサに反応してくれないので、釣れない状態になってしまうのです。 この件に関する詳細については、項目【エサを、いかに自然に落とすか】を参照して下さい。 |
|||||||||||||
| ②の「エサが海底(ベタ底)に付いたら仕掛けを上げる」 師:エサの着底はラインの変化で確認する 師:これができないと、この釣りは上達しない ★なので、師匠との釣りに同行する前、一人で木更津堤防へ行き、着底した時のライン変化を見る訓練をしてきたのです。 で、偶然にも初挑戦で1匹釣れちゃったのですがね! 師:エサが着底したら2〜3秒数えて仕掛けを上げろ 師:魚がヒットしていれば重くなるのでスグわかる ★この時、エサを海底に置く時間は2〜3秒と教わりました。 実際、師匠の聞き合わせのタイミングは2〜3秒です。 但し、近年は老眼の影響からか、5〜7秒、底にエサを置いたまま動かない時があります。 私しが、「聞き合わせのタイミング、ずいぶん遅いね!」と聞くと、「そう?」なんて言い返すので、 老眼でラインの微妙な変化が見えなくなったみたいです。(‾o‾) ★その後、関東で有名な名人から、このタイミングを見たり聞いたりしましたが実際はバラバラです。 皆さん、1〜6秒の間でした。 結論から言うと、実際、どのタイミング(時間)が良いかは好き好きの問題のようです。 師:海底にエサが到着する前にラインに違和感を感じたら即聞きアワセすること。 この際、着底の時のように2〜3秒待ってから聞きアワセするとエサを潰される危険性が高くなる。 (この件はタナでのアタリに対するレクチャー)
★私の釣り方は、海底にエサ置く時間が普通と違います。 落し込み釣りを始めた当時より0秒、エサが着底した瞬間に仕掛けを優しく上げます。 着底した瞬間に仕掛けを上げる理由は、エサが海底に付いたのか、それとも黒鯛がエサをくわえている『止まるアタリ』なのかの判断できないので、私は即座に『聞きアワセ』の動作に入ります。 この様に、私は海底でエサを置くスタイルの釣りはしないので、『海底イコール黒鯛のアタリ』と考え、即聞きアワセの動作行ないます。 今までの経験から、この止まるアタリが出た瞬間、即アワセ(聞きアワセ)をしないと、エサが潰されるだけで終わってしまうことが多ように感じています。 この件に関する詳細は、項目【一番難しいアタリについて 1ページ目】を参照して下さい。 ★参考: 聞き合わせのタイミングについて 師匠から教わった釣り方で、私が唯一マネをしていないのが、エサが着底した時の仕掛けを上げるタイミングです。 ここでマネをしない理由についてチョロリ説明しましょう。 私と師匠はこのタイミングが違う事から、1日の釣行で下記の結果となります。 結論を先に述べておきますが、1日の釣行で黒鯛の釣れる数は、私と師匠と殆ど変わりません。 その日の運と狙う場所の選択で、1匹多いか少ないかの釣果となり、勝ったり負けたりしています。 下表の例は、野島堤防での数字です。
以上結果の通り、トータル的なアタリの数には殆ど変化がないことがわかると思います。 常識的に考えると、エサを海底に置いておく時間が長ければ、必然的に黒鯛がエサをくわえるチャンスが増えるように感じます。 しかし、上のデータを見と、「実際には関係がないのではないか?」と思われるのではないでしょうか。 但し、このデータはツブ(カラス貝)を使った場合です。 エサがカニだと違いがあるかもしれません。 ちなみに、黒鯛シーズンは毎週のように1台の車で一緒に出かけていましたので、帰りの車の中では当日のアタリの数など、あらゆる情報を聞き勉強していました。 当日のアタリの数を聞くことで、聞き合わせのタイミングが釣果に関係があるかを、当時念入りに調べたのです。 以上に理由により、 聞き合わせのタイミングは「皆さんのお好きなタイミング(時間)でOK」との事となります。 「なぜ私と師匠のタイミングが違うか?」については、魚を掛けた瞬間の楽しみ方の違いだけです。 師匠曰く、 「黒鯛のアタリはものすごく小さいので、エサをくわえた後に出る「極小さな糸フケ(ライン変化)」を見てから魚を掛けたい」 「止まっているラインがチョコット動いた時の感動は最高」との事。 (師匠は、もよるアタリなんて言い方をしています) 「お前の釣り方では、竿を上げたら魚が掛かっていたという感じなので面白さが半減する」 「但し、海底(地底・ベタ底)より上側で止まるアタリやラインに違和感があったら、即聞きアワセするけどね!」 と指摘されました。 確かにその通りですが、私はエサを潰される屈辱を絶対に味わいたくないので仕方ないですね。(^o^) だって、東京湾の堤防では黒鯛の絶対数が少ないから、一日の平均的なアタリの数は4〜6回。 この4〜6回しかないチャンスを生かすも殺すも仕掛けを上げるタイミング1つなんですから・・・。 聞きアワセがコンマ何秒か早ければ、黒鯛がヒットする可能性が高くなるのですから・・・。 そして聞き合わせのタイミングが遅いと、エサを潰され、そして吐き出されてオシマイの時があるのですから・・・。 なので私は、着底イコール止まるアタリとの考えで釣りをしています。 タムラ曰く、 私が仕掛けを上げるタイミングを0秒にする理由はもう一つあります。 水深3〜4mの堤防に於いて、落し込み釣り(ヘチ釣り)で釣れる黒鯛のヒット率を水深毎に集計してみたのです。 すると下表の結果となりました。
以上のように、私が体験した底でのヒット率は、『海底(ベタ底)でヒットした』ではなく、『海底周辺でヒットした』だったのです。 もちろん、水中に沈み根や堤防の段差のようなものが海底にある場所ではこのデーターが狂ってきます。 この集計結果から考えると、どの水深で黒鯛がヒットするか全くわからないとの事です。 ただ底周辺でのヒット率が異常なくらい高いとの結果になるので、水深の浅い堤防では底周辺でのヒット率が高いと良く言われています。 本題に戻りますが、 釣りの最中、エサが底に付いていると思い、仕掛けを上げるまでのタイミング1〜6秒を数えていたとしましょう。 しかし実際は、海底より10cm上で黒鯛がエサをくわえていた(止まるアタリ)としたら、貴方は何秒で聞きアワセをしますか? なので、私はエサが着底したら、ラインに異変があったと時と同じように即聞きアワセをします。 ちなみに、釣り仲間との情報交換の際、「黒鯛が釣れたのは、タナ?それとも底?」との話を良くします。 この回答がタナであれば、「アタリがあったのは上からどのくらい? エサは?」と情報収集。 底と言われたら、「エサはなに?」と確認するだけで、「底からどのくらい上?」なんて聞く方は殆どいません。 なぜだろう? (‾o‾) 皆さんへの質問 日頃、「知らないうちにエサが潰されていた」とゆう経験は、誰もが体験しているはずです。 いつ潰されたのか想像が付く場合もあれば、何分前に潰されたのかわからないこともあります。 この時、このアタリを確実に取っていれば、1日のキャッチ数が何匹になるか計算できますよね? もちろん、バラシやスッポヌケがありますが、キャッチできる絶対数は増えるはずです。 では、皆さんに質問です! あなたはエサが着底した時、何秒のタイミングで仕掛けを上げる動作に移りますか? ムフフ・・ 私と同じ、0秒で即聞きアワセ? それとも一般的な1〜6秒待ってから仕掛けを上げる方法? |
|||||||||||||
| ③の「2〜3m外れた場所に仕掛けを再投入する」は、いかに効率良く黒鯛の近くにエサを落とすかを考えた釣り方です。 考え方としては、エサを基準に半径1m以内にいる黒鯛は、「食い気があれば、上から落ちて来るエサに高確率で反応し捕食する」と言う、黒鯛の習性を利用した攻め方となります。 この考えを基に探り方を考えると、 2〜3m外れた場所に仕掛けの再投入を繰り返すことにより、堤防全体をキッチリ探ることができるとの結論になります。 この考え方がどの程度の「信頼性」を持っているかについては、項目【実際目で見た捕食の瞬間】を参照して下さい。 落し込み釣りは、エサを落した場所で黒鯛が釣れなければ、この付近には黒鯛が居ないと判断します。 この為、別の場所への移動を繰り返しながら、黒鯛との偶然の出会いを求めて探り歩くのが基本となります。 名古屋方面の釣り人は、『一日何十キロ探る』など目標を立てて探り歩いているようです。 正にこの考え方による釣り方ですね! しかし、苦い経験も多々あります。 例えば、1分前に私がエサを落とした場所で釣られてしまった場合や、エサを海底に5分以上置きっぱなしの方に黒鯛がヒットした場合です。 師匠曰く、「運が悪かったと辞めよう」と言いますが、やはりショックです。 とは言え、トータルで考えると、今まで他の方が探っていた場所で、後から仕掛けを落とした私が魚を釣り上げる確立の方が断然高いので、師匠から教わった落し込み釣りの基本行動は正しいと実感できます。 でも、「この歩き回る釣り方がホントに正しいのか?」と疑問に思ったことは確かです。 そう感じたのは野島堤防で釣れる8割の魚は底周辺でヒットするからです。 「8割の魚が底周辺でヒットするなら、底周辺にエサを長時間漂わせていたほうが釣れる確立がアップするのではないか?」と言う疑問でした。 そう、2〜3m間隔で探る効率の良い移動は、黒鯛との出会いを増やすことは可能だと思いますが、底周辺にエサが漂う時間が非常に少ない事に疑問を抱いたのです。 「この時間配分、これでホントに良いのか?」と・・・。 野島堤防では8割の魚が底周辺でヒットするとの話は、この釣りをはじめた当初師匠から教わった話です。 そして経験を重ねる事で私も一人前の落し込み師となり、この割合は私の体験とも一致します。 「ヤハリこの割合は間違いない」と確信すると同時に、心の中のモヤモヤは更に膨れ上がります。
そんな感じの疑問が色々あり、この件に関する詳細については、当サイトの全て項目を読まれると、 どのような探り方が最も良いのか理解できると思います。 チャンチャン! 結論は、師匠から教わった『基本動作』が最も良い方法でした。 です! チャンチャン! 『底周辺にエサが漂う時間が非常に少なくなる事』は気にする必要はないって事でありますか・・・。 1時間釣りをしたと考えると、底周辺にエサが漂う時間なんて10〜15分ぐらいだろ! それ以外の45〜50分の釣りは無駄とゆうことじゃね〜か。 それを横からチャチャ入れおって! ちょっと表現を変えると、 落し込み釣りをこよなく愛する黒鯛師にとっては永遠の疑問と言える事柄だからね! 船長が「HPの文章を全部読めば」と記載した理由は、黒鯛がエサを捕食する時の行動を理解してほしかったからさ。 それでは、黒鯛の行動を下図を見ながら説明しよう! 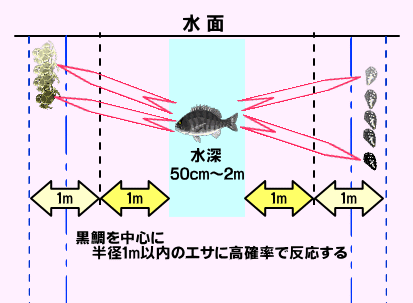 ここに記載する文章は、この後の項目【衝撃、実際に目で見た「捕食」の瞬間】で詳しく説明しているのだが、 簡単に説明すると・・・。 黒鯛が水面から落ちて来るエサに反応する範囲は、今までの調査である程度明らかになっている。 それは、黒鯛を中心とする半径1m以内にエサを落せは、高確率で反応するとの事。 そして、最大2mぐらいまではエサを追う事がわかっているのだが、追わない魚もいるので、 基本的には1m以内であれな反応するとの表現を使っている。 面白い現象としては、黒鯛の後方(尾びれ側)に落ちるエサにも反応する事。 但し、このデータは見える黒鯛と格闘した実験結果なので、海水のニゴリが濃い場合は反応する距離が狭まるかもしれない。 また、エサに反応しない場合もある。 それは、魚の活性が悪い場合、人間の気配を感じた場合、上から落ちてくるエサに不信感を抱いた場合(人間の罠である事を察知)、カラスガイの層に顔を向けガリガリしている場合などがある。 ちなみに、人間の私が見えている黒鯛の2m手前まで近づき、全く反応しない黒鯛の目の前20〜30cmの場所にそお〜っとエサを落しても見向きもされない事もある。 逆に、人間が落したエサに警戒し、勢い良く逃げる魚やスーっとゆっくり海底に沈んで行く(泳ぐ)魚もいる。 よって、食い気のある黒鯛と人間の罠である事に気付いていない黒鯛は、1m前後離れた場所に落下するエサに反応するとの結論となる。 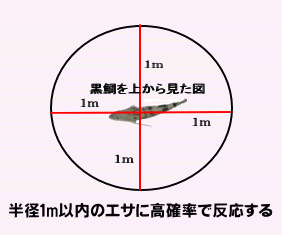 同様の考え方を、別の観点から説明すると上図の様になる。 黒鯛は水面から落ちてくるエサに対し、自分を中心に半径1m以内であれば反応する。 と言うことは、自分の身体より上方向から落ちてくる物は、360度全て見えているとの事。 もちろん、死角はあるだろうし、自分の身体より下方向のエサにどの程度反応するかは全く不明だ。 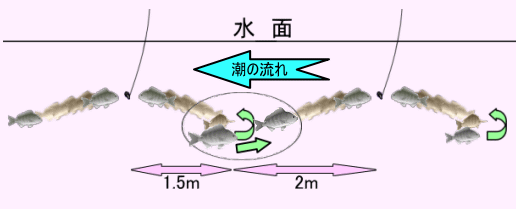 上図はエサを捕食する黒鯛の行動。 自分の後方(尾びれ)側のエサに対しては、クルっと反転しエサに突進する。 この時の反転スピードは目にも止まらぬ速さなんだよ。 参考:中心・丸印の場所の黒鯛は、前方と後方へ同時にエサを落すと、どちらに反応するかわからない。 通常は先に発見したエサに突進するが、後から投入したエサが捕食しやすい位置だと、捕食しやすい方を選び進路を変える時もある。 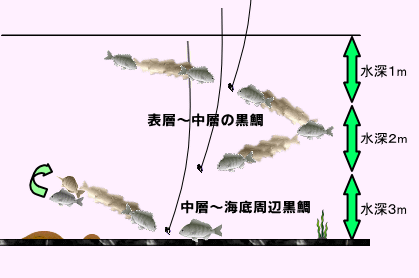 上図もエサを捕食する黒鯛の行動。 表層から海底周辺に生息する黒鯛がエサを発見してからエサに飛び付くまでを画像にした物。 表層から落下するエサに対し、素早く捕食する場合もあれば、不自然な動きをするエサの状態を目視し、見定めてから捕食する場合もある。 よって、エサを追い始める瞬間から捕食するまでの時間に統一性がない。 なので、中層の魚が海底までエサを追い掛けて捕食する事が多いに考えられる。 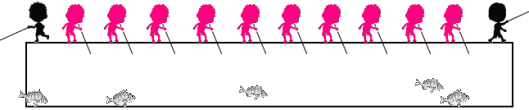 まとめ 黒鯛の捕食行動に関する事実が明らかになれば、おのずと最も効率の良い探り方を導き出すのは容易い。 以上の理由から、 上図の様に2〜3m間隔で堤防を探れば、『堤防全体の黒鯛を一通り探る事ができる』との結論となる。 そして、探る水深は表層から海底までとなるので、全ての水深に生息する黒鯛を狙うことが可能になる。 よって、底周辺でのヒット率が8割との事実があったとしても、どの水深に生息する黒鯛がヒットするかわからないので、落し込み釣りの基本通り、水面から海底まで秘伝のスピードで探り、仕掛け回収後は2〜3m離れた場所で再びエサを落し、表層から海底まで探る方法がベストとの考え方となります。 この2〜3m離れた場所に落とす秘訣は船長や師匠の佐藤さんが考えた秘伝の奥義ではありません。 先人の黒鯛師が試行錯誤のすえ編み出した、黒鯛の習性を利用した釣り方なのです。 落し込み釣りには色々な考え方があります。 その真髄を理解し習得した時、皆さんの黒鯛釣りがガラリと変わると思いますよ。 この釣りを考えた先人に対し、心から感謝しましょう♪ |
■落し込み釣り師の実力は、釣り師の行動から読み取る事ができる
黒鯛の落し込み釣りは、釣り人の「釣り方」を3分間見ていれば、その釣り人のレベルが上級者か中級者か初心者かが分かってしまいます。
「レベルが分かる」とは、非常に嫌な表現ですよね!
あえてこの表現を使った理由は、皆さんに落し込みの素晴らしさを体験して頂きたいからです。
特に私のホームページを読んで頂いた方に!
どこで判断できるのかと言うと、釣り方のスタイルで分かります。
そう、落し込み釣りの極意である、『基本動作ができているか?』、それとも『自己流か?』で判断できちゃうんです。
恐ろしいでしょ!
表現を変えれば、落し込み釣りはこんな単純で簡単な釣り方なのに、釣り方の基本を知らない方が沢山いらっしゃると言うことです。
では、「釣り雑誌やビデオで勉強しても良く理解できない落し込み釣りを、どのようにすれば最短時間で会得することができるか?」について、下記にまとめてみました。
| □奥義・その2 『釣り師の行動確認』 |
| 現在、壁にぶちあたっている方は日頃から同じ堤防に通い、日頃から魚を良く釣る方の基本行動を目で見て覚えるのが良い方法です。 私がなぜたった2ヶ月で名人と呼ばれるようになったか? 結論は簡単、名人の釣り方を目で見て真似をしたからです。 仕掛けを上げて歩いている時は、いつも遠くにいる師匠の動きを横目でチェックしていました。 そして、釣り方を見て良く質問をしました。 同様に狙っている場所についても良く質問しました。 例:あそこの場所だけ沖に仕掛けを投げて探っているけどなぜ? 師:あの場所は底に根ガカリが多く、今までの経験で釣れる確立が高いから 例:あの角周辺だけ3回探り直したよね、なぜ? 師:あそこは潮のブツケで潮の流れがあるからエサの投入位置により仕掛けの流れる方向が変わるんだよ! まずはヘチを探り、次はラインを3mぐらい出して潮の上にチョイ投げ! で、着底した瞬間エサがこの辺に流れて来るだろ。ココは良くヒットするんだよ! 次はあの辺りにチョイ投げすれば、ホラ、潮の流れが早くて堤防のヘチを探れなかった場所を綺麗にチェックできるだろ。 なんて会話をしながら秘密のポイントや探り方を覚えたのです。 この基本行動は、どこの堤防でも同じで、地元の釣り師のエサの投入地点をチェックすれば簡単に覚える事ができます。 ちなみに、釣りの世界では師匠と呼ばれる釣り師は大勢おります。 そして弟子は師匠の教えに従い釣りを覚え上達します。 しかし、その師匠の釣りレベルや知識の度合いで弟子の育ち方が変わってきます。 そう、釣り方や考え方が、釣れない釣り方になってしまう危険性があるのです。 表現を変えると、釣れる可能性の少ない釣り方を教わってしまうと、その釣り方に固執し、いつまでたっても釣れない釣り師のままとなり、最終的には釣りを止める方もでてきます。 師匠が弟子に伝える、黒鯛の習性を考えた釣り方(自己理論)についても一緒です。 「黒鯛のアタリは小さい。魚がエサを飲み込むまでラインを送り続けろ」とか、 「エサは釣れる可能性の高い底を這わせるように潮に流してゆくのがベスト」など、 師匠が釣り場に通い得た知識を弟子に強制する釣り師は今でも多いです。 私の出会った師匠の佐藤さんは、偶然にも野島堤防の名人と呼ばれる凄い方でした。 よって、名人の釣りを見て覚えたのでスグに上手くなったのです。 でも実際、佐藤さんと釣りに行って黒鯛を何匹も釣るまでは、聞かされた話の半分はウソのように感じていたのは確かです。 釣り師は、偉そうに釣り自慢をする方が多いですからね!(‾o‾) でも、名人である事を確信してからは、その出会いを神様に感謝しました。 上で述べた自己理論についても、当時、佐藤さんの話す全ての話が正確なものであり、確たる証拠のない事柄については「正確な理由はわからない」と回答するのです。 で、わからない事については、「多分、こうこうなのだと思う」との回答が帰ってきます。 なので、自論強制させる事はなく、落し込み釣りの真実を私は学びました。 そして時は過ぎ、初心者当時に聞かされた全ての話が正しかった事に気づきました。 とは言え、そんな名人級の黒鯛師に釣り場では簡単には会えないと思いますので、その対策を下の項目でチョロリ説明します。 |
| □奥義・その3 『ストーカー作戦』 |
| 自分のホームグラウンドで、日頃から黒鯛を良く釣る方の後を、女性を狙うストーカーのように追い掛けるのがストーカー作戦です。 自分の仕掛けを落としている時にはラインの動きに集中しますが、仕掛けを上げている場合や、堤防の上を歩いている時などは、常に狙いを付けた釣り師の行動を横目で確認します。 すると、その堤防の狙い方が見えてきます。 「堤防全体はタナと底を両方狙っている」とか、 「あそこの場所だけ、底周辺を丹念に探り、エサを潮に乗せて流す釣り方をする」とか、 「あそこの場所だけ、落し込みで探る回数が他の場所に比べて多いし、けっこうシツコク狙っている」とか、 「あそこの場所だけ、ラインを出し遠投。底を丹念に探っている。もしかしたら根がある?」とか、 「エサは何を使っているか?」とか、まあ色々の情報を得られるはずです。 釣り師の行動は以外と単純で、普段から釣れる可能性の高い場所は丹念に狙います。 また、当日アタリのあった周辺を繰り返し攻めたり、普段から魚の付きやすい根のある場所を攻めたりと、その方の釣り方を見ていれば、はじめて訪れる堤防でも攻め方のパターンがわかってきます。 しかし、釣れない釣り師の行動はと言うと、あまり堤防の上を動かず、実績のある場所周辺で粘る方は多いです。 なので、動き回る釣り師を探すのも、釣り場のクセを学ぶのに良い作戦です。 ストーカー作戦は各堤防のポイントを知り、名人の釣り方や狙い方を覚えるだけではありません。 当日の風向きや風速、下げ潮・上げ潮で潮の流れる場所の観察、狙い目の潮位など、どの様な条件でどこの堤防に乗るかを学ぶことも重要です。 |
| □奥義・その4 『金魚のフン作戦』 |
| この作戦は普段から黒鯛を良く釣る方と親しくなり、一緒に釣りをする機会を増やす作戦です。 この作戦のメリットは、休みの度に同じ黒鯛師をストーカーできるメリットと以外に、会話することによる情報収集の役割を兼ねています。 まあ、「釣れる様になる為には何でもやる」ってゆう、根性が大切だと言うことですね! |
■1匹の黒鯛を釣る為のプロセス
私が思うに、落し込み釣りをマスターした段階で、1匹の黒鯛を釣るプロセスを考えると下記のようになります。
| 運 | 当日の釣果を左右するのは”運”です。 1匹の黒鯛を釣るプロセスを10割として考えると、運が5割を占めます。 運が良ければ釣り方など関係なく黒鯛が釣れます。 しかし運が悪いと、いくら頑張っても黒鯛は釣れません。 もちろん、この強運を自分の物にするには下の内容の努力が必要です。 |
|
| 釣り方 | 釣り方の問題は全体の2割5分を占めます。 最も重要と思われる釣り方の問題は、実は2割5分程度なのです。 驚きでしょ? |
|
| 状況判断 | 当日攻める釣り場の選択は、 潮位/潮の流れる向き/潮の速さ/風向き/風の強さ/ニゴリの濃度、 最近の状況など、様々な条件を集計し判断します。 この、どこを攻めるかで釣果が変動しますので、状況判断が占める割合は2割5分となります。 釣り大会などで競争する場合は、この状況判断と運が釣果を左右します。 |
|
| 師匠の格言 | 参考までに、師匠が良く話す言葉をご紹介しましょう。 「運さえあれば誰でも1匹は釣れる」 「2匹目の魚を釣ってこそ、釣れたのではなく、釣ったに変わる」 「釣れた魚のサイズは運であり、数を釣る事に意味がある」と話しています。 但し、魚のサイズに付いては、釣り仲間に対する師匠のヒガミです。 師匠は、黒鯛人生において数は良く釣るのですが魚の大きさに恵まれません。 この為、弟子全員に56cm・3kg以上の大物を先に釣られてしまっており、 1人イジケテいるのです。(^o^) とは言え、56cm・3kオーバーの黒鯛を2匹、2002年にやっと釣る事ができました。 良かったね!(^_^)v |
|
■上達の早い方・遅い方
最近やっと分かったのです。
良く魚を「釣る方」と「なかなか釣れない方」の違いについて。
言葉を変えれば、上達の「早い方」と「遅い方」です。
□上達の早い方
他人の意見を素直に聞き入れ、その内容を実行することができる方です。
表現を変えると、センスが良い方です。
上手い釣り人の釣り方を良く見て勉強し、マネができる方です。
また、自分のプライドを捨て、魚を釣った釣り人に情報を聞きに行く勇気のある方です。
分かりやすい表現では、TVの釣り番組・児島玲子ちゃんの会話を思い出して下さい。
「今、どの変のタナで釣れたんですか?」
「どんなアクションで誘っているのですか?」
「ちょっと変わった仕掛けですね! それ効果があるんですか?」
と、情報収集する勇気のある方です。
□上達の遅い方
ホントは真似をしたいのだけれど、思ったように身体が動かない方です。
目で見て頭の中では分かっているのですが、なかなか真似をする事ができません。
研究熱心で努力家の方に多いのが特長で、その努力には頭が下がります。
もちろん、この様な方から釣り場で質問されたら丁寧に回答しています。
「分かった!分かった!」と素っ気ない態度で返答する方。
メンドクサイとの考えや、長年行なってきた自分の釣りスタイルを変えたくないので全く聞く耳をも持たない方も多いです。
まあ、簡単に言うと「我が道を行く」とゆうタイプの方々が多いように感じます。
長年釣りをして来たプライドが邪魔をし他人のアドバイスを受け入れたくないようです。
人間色々な性格の方がいらっしゃいます。
釣りが好きで楽しんでいるのだから、かかわるのは止めましょう。
■最後に
このページに記載した釣り方の基本動作こそが、関東流.落と込み釣りの極意です。
基本行動は簡単ですが、一つ一つの動作や考え方には全てに理由があり、その全ての知識を生かすことにより、より多くの黒鯛との出会うことができます。
正直申し上げて、この落し込み釣りを『黒鯛が釣れる釣り方』として確立した先輩の釣り師の方々の努力には頭が下がります。
多分、この釣り方を確立するために膨大な時間を費やし、数え切れないほどの黒鯛を釣り、そして「愛する黒鯛を1匹でも多く釣ろう」とする努力と知恵。
黒鯛釣りに狂った釣り師でないと考え出せなかった釣法だと思います。
この釣り方に関する動作や考え方については、これ以降のページで記載しておりますが、その行動一つ一つの意味が理解できた時、貴方はきっと先輩釣り師の方に敬意を払うとともに、後世へ託されたこの釣り方に感謝する思います。