黒鯛釣りのファンは、『昼専門の釣り人と夜専門の釣り人』とに分かれます。
私や師匠は性格的に、夜の黒鯛狙いが好きではありません。
どうも釣り方が単調で合わないのです。
この為、これから記載する文章は、殆ど参考にならないと思います。
なぜなら夜間に気合を入れて黒鯛狙いをしたことがないので、参考にならないと思います。
夜釣りファンの皆様、ごめんなさい。
![]()
はじめに申し上げますが、夜の釣りは大好きです。
メインは、ルアーによるシーバス狙い、エサ釣りのメバル・カサゴです。
目の悪い方にとっては暗くて周囲が良く見えない関係から、夜は嫌いだと言われる方は多いのです。
私は特別目が良いので、一般の方が通常ヘッドライトを使う状況でも私は使いません。
都心のわずかな光でハリを結んだり、エサを付けてたりすることができます。
あるお客さまに言われたのですが、
「船長の先祖は盗賊だったのではないか?」
「盗賊の生まれ変わりだから夜の目が利くんじゃないの?」なんて話を聞き、大笑いした記憶があります。
実は、盗賊じゃないけど、ジイちゃんのオヤジは茨城県那珂湊で廻船問屋をやっていたそうです。
昔は大棚で、ジイちゃんのオヤジがバクチに手を出しヤバクしちゃったみたいです。
まるで時代劇の話みたいですね!
俺の先祖って、時代劇に出てくるような船に乗っていたのかな〜?
ここで紹介する釣り方は師匠に教えてもらった釣り方で、漁師に転職した後、時間がある時に師匠と一緒に試しました。
一人でも試しましたが、二人で試したほうが釣果に差が出るので、どのような探り方が効果的かを勉強するには良い機会となりました。
【目次】
1.釣り方紹介
2.なぜ夜間は、仕掛けを止める時間が長いのか?
3.暗くなった瞬間に突然釣れなくなる現象とは?
1.釣り方紹介
考え方としては、夜の釣りと昼の釣りは多少共通点がありますが、全く別の釣りと考えた方が良いです。
数を釣る為には、昼の釣りと同様に2〜3m間隔で探り回ります。
釣り方の違いは「聞きアワセのタイミング」と、同じ場所へ仕掛けを「何回も落す」ことです。
パターンは2通りありますが、どちらが良いかは経験不足で分かりません。
| ■釣り方 | |||
| ①あらかじめ指定した水深まで仕掛けを落とし5〜10秒待ちます。 タナ釣りなら探りたい水深分ラインを出し指定した水深でラインを止めし5〜10秒待つ。 底釣りの場合は、エサが着底したらし5〜10秒待つ。 アタリは竿に伝わる振動で判断します。(コンと竿に伝わる) この時、エサを飲ませる為にラインを送り込む釣り方があるが私は良く知らない。 アタリがなかったら、2〜3m離れた場所に再び仕掛けを投入し、この釣り方を繰り返します。 ◎コメント 潮の流れがある時には、潮に載せるように堤防の上を歩きます。 |
|||
| ②あらかじめ指定した水深まで仕掛けを落とし約5秒待ちます。 タナ釣りなら探りたい水深分ラインを出し指定した水深でラインを止めし約5秒待つ。 底釣りの場合は、エサが着底したらし5秒待つ。 約5秒後、50cm〜1mほど仕掛けを上げ、再びその場所へ仕掛けを落とします。 (この時、優しく仕掛けを上げる事と、秘伝のスピードで落すことが重要) 3〜5秒後、再び50cm〜1mほど仕掛けを持ち上げ、再びその場所へ仕掛けを落とします。 3〜5秒後、仕掛けを上げ回収。(ワンセット終了) 2〜3m離れた場所に再び仕掛けを投入し、この釣り方を繰り返します。 ◎コメント:私の好きな釣り方 私の好きな釣り方は、どちらかと言うとコッチです。 また、落す回数でヒット率が違うことがわかっています。
2回目の落しと3回目の落しでの割合には殆ど差がありません。 強いて申し上げると、若干2回目の落しのほうがアタリが多いです。 尚、その日の魚の活性によって2回目のヒット率の割合が高い場合があります。 このような場合は時間効率を考え、3回目の落しは行わず、広範囲を探る釣り方に切り替えます。 ◎コメント:潮が動いている場合の釣り方 潮が動いている場合は、潮の流れるスピードにあわせて歩きながら、仕掛けを上下し探るのが効率が良いです。 また、仕掛けの再投入は、2〜3m間隔で落しても良いし、下記の図のように、仕掛を潮に乗せながらエサをジグザグ状態で探る方法も効果的です。 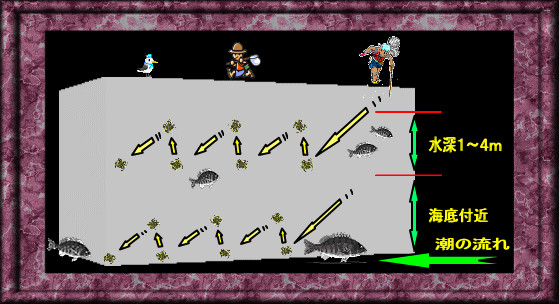 |
2.なぜ夜間は、仕掛けを止める時間が長いのか?
この件は色々な意見があると思いますが、私の想像では、エサの発見に時間が掛かるからだと思います。
昼間の場合、目や身体の側線でエサの存在を確認し、素早く捕食できるるのだと思うのですが、夜の場合、この動作が確実に遅くなります。
この為、エサの存在を魚に知らせる為に5秒以上エサを止めて置いたり、エサを上下にさせる動作を行います。
■参考:夜光虫
タナ釣りにおける黒鯛やシーバスの捕食行動は『夜光虫の動き』で判断する事ができます。
1回目のエサを落とした時にはエサの存在に気が付かないようで、1回目に落とした仕掛けを優しく持ち上げる時にエサに反応する魚は多いです。
![]()
よって、2回目の落としでエサに興味を示し(エサの存在を知り)パクリとくわえる確率が上がります。
![]()
アタリがなかったら2回目に落とした仕掛けを優しく上げる動作で、未だ近くでエサの存在に気づかない魚にアプローチ。
![]()
よって、3回目に落としたエサに興味を示し(エサの存在を知り)パクリとくわえる確率が高くなります。
![]()
通常はこのパターンで別の場所へ移動しますが、4回目・5回目を落としても釣れる可能性はあります。
ただ効率の悪い釣り方になるので行わないだけです。
黒鯛の行動は夜光虫の動きを見る限り、仕掛けを落す時より引き上げている時のほうが反応が良いです。
イメージとしては、仕掛けを上げている時に、その場所へ向かってスーと一直線で近づいてくる感じです。
この現象は昼間の行動と正反対となります。
まとめると、昼間はエサを引き上げる時の水の抵抗音に警戒しますが、夜は水の抵抗音で興味を示し、エサの存在を知るって事ですね! (^_^)b
■参考:夜間は泳ぐスピードが遅くなる
夜間における黒鯛の泳ぐスピードは、昼間捕食するスピードと比べると、1/2から1/4ぐらい遅くなると感じています。
この件は私の推測ですので参考程度に考えてください。
狙い方はタナ釣りです。
その理由の一つは、夜光虫の動きを見てわかりました。
黒鯛はエサのある場所に向かい、スーっとゆっくり近づきます。
この時の泳ぎ方は、昼間見慣れている俊敏な動きではありません。
夜光虫の動きで、「エサに近づいたな〜」と思った瞬間、竿先にコンとアタリが伝わり、聞きアワセしヤリトリ開始となります。
アタリがコンとあった瞬間に、頭の中で「これは黒鯛だ!」と思っていると、予想通り黒鯛なのです。
で、「俺って天才!」と声に出して自己満足します。
ちなみに、近づいてきた魚がシーバスの場合は、黒鯛より若干早く動きます。
そして、ラインを上げ下げする際の動きが全く違いますので、その動きを見ていると黒鯛かシーバスなのかの判断ができるようになります。
とは言え、魚の判別の成功率は70%ぐらい。
まあ30%は失敗(その魚は60UPのスズキ)するけど、この数字、天才としか思えないでしょ! アハハ・・・
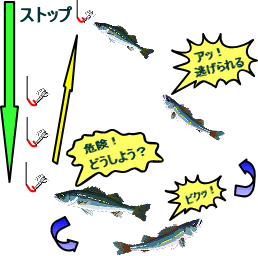
上図が一般的なシーバスの行動です。
エサの上げ下げにより、一旦堤防から離れる方向へサーと泳ぎ、再びエサに近づきます。
黒鯛はこのような行動は取らず、スーと近づき、警戒した場合はその場で動かなかったり、ゆっくり方向を変え泳ぎ去ります。
多分、黒鯛は身体の側線でエサの存在を確認し、目で確認できる距離まで注意しながら近付くのだと思います。
『思います!』と言うより、そのように見えます。
もちろん、夜光虫が少ない条件では魚の動きがわかりませんので、どのような行動を取っているのかわかりません。
もう一つの行動について、
夜間、暗い場所で黒鯛やシーバスがヒットすると面白い行動を取ります。
その行動とは、魚とのヤリトリの最中、障害物に近づかないように泳ぐのです。
昼間の黒鯛は、近くの障害物に近づこうとしたり、障害物に逃げ込んだりします。
しかし、夜の黒鯛は俊敏な泳ぎを止め、障害物に激突しないよう慎重に泳ぎ回ります。
昼間のシーバスも黒鯛ほどではありませんが障害物に逃げ込もうとします。
それが夜間では障害物の無い方向へ逃げる魚が多くなるのです。
私の推測で恐縮ですが、障害物に激突することを避けているように感じるのです。
なぜそう思うのかと言うと、夜間のヤリトリの最中、岸壁や障害物に激突する黒鯛とシーバスの数が昼間に比べてとても多いからです。
そして激突した魚をマジマジと見ると、口周辺・頭・胸付近から出血していたり、尾ビレをバッサリと切り大量出血する魚が非常に目立つからです。
昼間は尾ビレを切る魚はいますが、障害物に激突する魚は滅多にいませんからね!
なので、夜間に激突する魚の数が多く感じられるのです。
そう、魚も人間同様に怪我をしたくないから障害物に近づかないのだと思います。
なので、夜釣りではシャンボ黒鯛が簡単に釣れる可能性があるということですね!
3.暗くなった瞬間に突然釣れなくなる現象とは?
これは実際に私が何度も体験している出来事です。
■堤防の場合
堤防の場合は、残念なことに5,6回しか体験していません。
その内3回は神奈川県.野島堤防で、エサはツブ(カラス貝)とカニです。
状況的には5〜15分間隔でアタリがあり黒鯛がヒットします。
薄暗い時間までは釣果に変化がなかったのですが、真っ暗になった瞬間アタリが少なくなりました。
アタリが全く無い訳ではありませんが、10〜20分に1回のペースに激減しました。
ちなみに、暗くなった際、昼間の釣り方では殆どアタリがでませんので注意が必要です。
釣り方も、夜の待ち釣りスタイル又は、上下運動をするスタイルに切り替えましょう。
余談ですが、私は暗くなった瞬間より「カニエサ」に交換します。
薄暗い時間まではツブで問題なく釣れるのですが、暗くなるとエサの発見のしやすさを考え、動きのあるカニに変えます。
釣り仲間の話では、真っ暗な夜中でも「ツブ」で釣れるそうです。
私は釣った事はありませんが・・・。
昼の釣り師は、イソメやカニなどの生きたエサを持っておりませんので、暗くなった後もツブで通します。
この話しは、多くの釣り師から聞く内容ですので信頼できる話です。
再び余談ですが、落し込み釣りを夜からはじめられた方は、なかなか昼に釣りに馴染めないみたいです。
その結果、昼の釣りにもかかわらず夜のスタイルで釣りをしてしまう関係で釣果が一向に伸びません。
なので、昼と夜は全く別の釣りと認識を改める必要があります。
■船からの場合
船からの場合も堤防同様にアタリの数が急激に減ります。
使用するエサは、カニとエビです。
状況的には、2〜10分間隔(平均3,4分)でアタリがあり、ウキウキしながら黒鯛との格闘を楽しんでいる感じです。
その格闘は薄暗い時間まで続きましたが、真っ暗になった瞬間アタリがピタっと止まるのです。
この体験は10回を超え、入れ食いではないが良い感じで釣れている状況&シーバス入れ食いの時も含めると計算できないくらい体験しています。
釣れなくなる理由については、私の想像ですが、エサの動きに問題があると思っています。
船の場合、堤防の上と違い、潮と風の影響で常に船が動いています。
この動きの為、エサを1箇所に5〜10秒間止めて置けないので、エサを引っ張ってしまうような感じとなります。
この不自然な動きが魚へ警戒心を与えるのだと思います。
■まとめ
黒鯛の捕食行動が昼と夜とで違うのは、エサの発見が遅れるからだと思っております。
夜のイソメ類が実績がある要因は、「臭いと動きでアプローチ」するからではないでしょうか?
またイソメ類は、海中で「青白く光る」と言われますが、私は光った瞬間を見たことがありませんので、この件は信じていません。
夜釣りに関する釣り方は、残念ですがこの程度しかわかりません。ペコリ
どこぞのサイトで詳しく説明されている文章があればよいですね! (‾o‾)ノ
■余談:夜間のシーバスの行動
皆さん、シーバスは夜行性と言われています。
ホントでしょうか? 私は疑っている一人です。
エサ釣りにおけるシーバス狙いの場合、
昼と夜とでアタリの出方や釣り方に違いが生じると思いますか?
答えは、「違いが生じる」です。
黒鯛同様に、夜間の行動はノロマとなり、エサの発見から逃げ回る行動まで俊敏さが無くなります。
一般的には、シーバスは夜間良く釣れると思われがちですが、実際は明るい時間帯が良く釣れます。
ルアー・エサ釣り共に、夜は獲物の発見が遅れますので、真っ暗な場所では食いが悪くなります。
但し、黒鯛との違いは、街灯や工場などの明りの周辺に集まる習性を持っていることです。
シーバスは、小魚が集まりやすく獲物を捕食しやすい明るい場所が好きなようです。
しかし、黒鯛は光に集まる習性はないように感じます。
例えば、薄暗くなる寸前まで、橋げたなどの障害物回りで頻繁にアタリがあつたと考えてください。
暗くなり、その場所が街灯の明りで昼間の様に明るいのにもかかわらず釣れないのです。
原因は全く分かりません。
とても不思議です。
まあ、どうでも良いことですね!
![]()
![]() 【ニゴリの移動に付いて】
【ニゴリの移動に付いて】